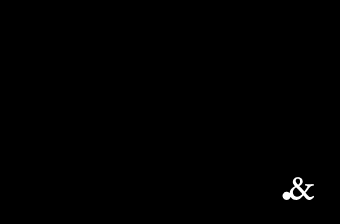- Cases
問われるのは「空間の活用方法」 長谷工×ドットアンド×Mogura 3社によるメタバース企画から見えてきたこと
「住まいと暮らしの未来のあたりまえ」をつくるべく、メタバースを活用したプロジェクトに長期的に取り組んでいる長谷工グループ。2024年11月にはプロジェクトの第三弾として「メタバース家具コーディネートサービス」を開始し、マンション購入を検討しているお客様に対して、バーチャル空間で部屋のコーディネートを体験していただく試みを実施しました。最初のパートナーとして、家具メーカーの良品計画と協働。購入可能な実際の家具を3D空間に自由に配置できる上、多人数での共有も可能。メタバースを活用して、お客様にこれからの住まいを想像していただくサービスをスタートさせました。
このメタバース企画は、長谷工アネシス・ドットアンド・Moguraの3社共同で進行されています。今記事では、3社代表の6名の座談会形式で、プロジェクトの初段階から振り返りながら、見えてきた課題と今後の挑戦のポイントについて迫りました(座談会進行:ドットアンド代表・野田)。
議論を重ねる中で生まれたメタバース活用のアイデア
ポイント
・今回発表された「メタバース家具コーディネートサービス」とは?
・ドットアンドとMoguraは今企画にどのようなかたちで関わることになったのか?
――本日はよろしくお願いいたします。まずは、長谷工アネシスの鈴木様と谷沖様の現在の所属と、職務上のミッションについて紹介いただけますか?

株式会社長谷工アネシス 鈴木様(以下、鈴木):
長谷工アネシスの価値創生部門に所属しており、主な業務は新規事業開発です。その中でも私はICT活用推進部に所属しており、マンション内へのICTの導入による新しい価値の創出や、既存事業へのICT導入による業務プロセスの改善などを担当しております。

株式会社長谷工アネシス 谷沖様(以下、谷沖):
同じく長谷工アネシスの価値創生部門に所属しておりますが、私は長谷工グループ全体のITを統括するIT推進部に所属しております。主な業務としては、新規事業開発に伴うシステム開発や長谷工グループのDX案件の推進・サポートを担当しております。
――まず鈴木さんに伺います。長谷工がメタバースプロジェクトを立ち上げた経緯と、その狙いをお聞かせください。
鈴木:
そもそも価値創生部門は、ICT活用推進部、IT推進部、FIT開発部、CR推進部、グループカスタマーセンターから構成されています。
これまでは各部署が個別に業務を推進していましたが、2023年にチャレンジプロジェクトを立ち上げました。これは、部門を横断する形でやりたい人が手を挙げて進めていくもので、その第一号案件がこのメタバースプロジェクトです。
広くDXが推進されている昨今、「メタバース」も視野には入っていましたが、ICT活用推進部としてはまだ手が出せていない分野でした。そこでチャレンジプロジェクトが立ち上がったことで、調査段階で止まっていたメタバースに取り組むことになりました。
大きくはトップダウンで始まりましたが、メンバーの中からやりたいという声が上がり、組織的にはボトムアップの形で取り組んでいます。
――現在は谷沖さんをリーダーの一人として、メタバース実証を推進していますが、改めてこの事業の概要を教えてください。
谷沖:
正式名称は「メタバース家具コーディネートサービス」ですね。お客様がご購入されたお部屋や、実際にお住まいの部屋を再現したメタバース空間で、家具やインテリアをご検討いただけるサービスです。
 (「メタバース家具コーディネートサービス」では、アバターを使ってバーチャルに再現された部屋の中を移動しながら見て回れます)
(「メタバース家具コーディネートサービス」では、アバターを使ってバーチャルに再現された部屋の中を移動しながら見て回れます)
 (複数人で同じバーチャル空間に入室。コーディネーターと相談しながらデザインを決められます)
(複数人で同じバーチャル空間に入室。コーディネーターと相談しながらデザインを決められます)
 (無印良品で販売されている家具を選び、バーチャル空間に自由に配置できます)
(無印良品で販売されている家具を選び、バーチャル空間に自由に配置できます)
 (家具の配置は自由に変更可能。家族構成にあわせたコーディネートを練る際に便利です)
(家具の配置は自由に変更可能。家族構成にあわせたコーディネートを練る際に便利です)
このサービスでは、お客様自身で家具のコーディネートをお試しいただくことができます。さらに、部屋の間取りや家族構成に合わせたプロのインテリアコーディネーターによるコーディネートを見て体感したり、メタバース空間内で家具を動かしながら、コーディネーターに相談することも可能です。

 (バーチャルで使用した家具はそのままオンラインで購入手続きが可能です)
(バーチャルで使用した家具はそのままオンラインで購入手続きが可能です)
バーチャル空間は長谷工の保有するBIMデータを用いて制作しているため、実際のお部屋に非常に近いものになっています。居住前で実際の部屋を見られない状態でも、家具を置いた場合の雰囲気や、家具が置けるかどうかの検討にご利用いただけます。
また、現在は実証フェーズでクローズド展開中のため、特定の新築物件のみをサービス提供対象にしています。
――ありがとうございます。私(ドットアンド代表:野田)と(Mogura社代表の)久保田さんから、ドットアンドとMoguraの支援内容と体制について説明します。もともとドットアンドとMoguraは、本件の立ち上げ段階からタッグを組み、メタバースの市場動向調査プロジェクトを開始しました。その後、構想策定フェーズ、具体的な各施策の設計フェーズを経て、現在は実証フェーズに入ってきています。

ドットアンドは、実証部分の設計を含むビジネス面とサービスデザイン全般を担当し、Moguraはメタバースに関する最新知見の随時インプットと、メタバースPFの選定、システムのUI設計と実装面を担当しています。現在ドットアンドからは、全体統括で私が入り、ビジネス設計、サービス設計でそれぞれ担当者をアサインしています。

久保田:
Moguraは、企業や自治体、行政に対して、メタバースやXRといったバーチャル領域のテーマの推進を支援する事業を展開しています。
また、業界メディアやカンファレンスに携わってきた経験から、世の中での使われ方、成功事例、課題点、技術動向などを把握しております。「どのプラットフォームを使えばいいのか」「ユーザーにとって良いものはどれなのか」といった目利きができる存在として、今回、市場動向調査から企画、開発まで一貫して担当させていただいております。
私はMogura側の体制の統括として初期から企画部分に参画させて頂いています。現在の開発フェーズでは、プロジェクトマネージャーの永井と、アシスタント2名の計3名でご支援をさせて頂いております。
――これまでのプロジェクト推進における、長谷工の皆様と支援チームの役割分担や、日々の検討の進め方についてお聞かせください。
谷沖:
現在は週に1回、2時間の定例会を開催し、そこで大きな方針の決定や議論などを行っています。その舵取りはドットアンド野田さんにしていただき、開発部分は永井さんに、プロモーションやUI/UXデザインは椋野さんに担当いただいています。
定例会の中で重要な方針については決定しつつ、具体検討が必要な事項については、各自持ち帰りまた次回の定例会で議論をする、との流れが基本です。長谷工側で社内確認や調整・承認が必要な点は持ち帰った上で社内検討しています。また、日々のやり取りについては、Teamsを使って連絡や情報共有をさせ検討し、フィードバックを共有させていただいた上で進めていく――。そのような流れにしております。
――Moguraの永井さんと、ドットアンドの椋野さんにそれぞれの観点からお伺いしたいのですが、構想策定、設計、システム構築、実証といったフェーズごとに、どのような動き方をされていますか? また、その関わり方や役割分担がどのように変化してきたかを教えてください。

永井:
Moguraの開発統括の永井です。本プロジェクトにはビジネスの方向性や目標がある程度決まった段階で参画し、そこから開発に関わっています。
参画後は、サービスで具体的に実現したいことをヒアリングし、議論を重ねた上で、実現に向けたメタバースPFの選定、システム構成の検討を行いました。その上で最適なチームを編成し、スケジュール管理などを行いながら開発を進めています。具体的な要件については、重要な点は長谷工様と協議しながら決定していますが、ある程度の裁量を与えていただいている部分もあるため、スピーディーに開発を進められていると感じています。

椋野:
私はプロジェクトの初期から参画していますが、当初はまだ何をするか決まっていない状態で、「メタバース」というキーワードがあるのみでした。当時はMoguraさんが中心となって市場調査や技術的な観点でのリサーチを行いつつ、2030年を見据えたメタバースの新しいサービスについて、未来志向の情報収集もしていました。
その上で、どのようなサービスを作るのかを何度も議論し、様々なアイデアを出し合ってきました。サービスデザインの領域では様々な事業の作り方があり、ユーザーの課題解決を目的とするアプローチもあります。ですが、今回はメタバースがまだ浸透していないフェーズであるため、世の中の変化や技術の進化を考慮した未来志向のリサーチも進めていました。
ただし、未来的になりすぎても現実感がないため、長谷工様のBIMデータや既存のアセット、日々の業務で感じている課題などを考慮し、現実的な要素も組み合わせながらアイデアを出し合いました。そして最終的には、「メタバースコーディネートサービス」というアイデアを発展させていきました。
新規サービスに挑戦する中で見えてきたハードル
ポイント
・ピンと来ない人に「メタバース」をどのように理解してもらうか?
・実際にサービスに触れたお客様からの反応は?
――これまでプロジェクトを進めてきた中で、困難に感じたことはありますか? また、そのようなハードルとぶつかった時に、どのように乗り越えたのかを教えてください。
谷沖:
社内外との調整が難しかったです。そもそもメタバース自体、長谷工には一切の馴染みがない分野だったため、まず私たち自身が学ぶ必要がありました。そこで、Moguraさんのご協力によって、現在世の中で実現されているメタバース・VRのサービスや機器を様々体験させてもらうことが第一歩でした。
社外との調整では、家具メーカー様との連携も難航し、ようやく良品計画様と協業できることになりましたが、コンタクトを取ること自体が最初のハードルでした。
それから社内の調整ですね。長谷工グループには様々な事業があり、グループ内の各社ごとに考え方や方針が異なるため、取り組みへの理解と協力を得ることも困難でした。
――社内での合意形成はどのように進められたのでしょうか?
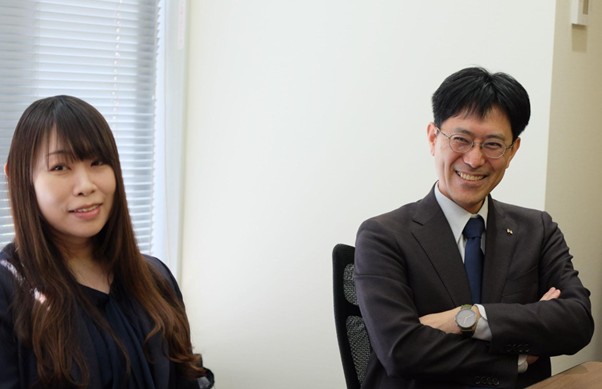
谷沖:
そうですね……「とりあえず1回やらせてください」とお願いすることでしょうか(笑)。
鈴木:
まだ完全に乗り越えられているわけではないので(笑)。正直に申しますと、関係各所とぶつかり稽古をしている段階だと思います。
谷沖:
ただ、ぶつかったらぶつかっただけ、少しずつご理解をいただくことができているような感触はあります。
――メンバーの皆様が強い意志を持って各部署と調整されていることは、外部にも伝わってきています。その熱意が周囲を動かす力になっているのではないでしょうか。ちなみに、お話に出ていたMogura主催の体験会はいかがでしたか?
谷沖:
とても勉強になりました。それなりにメタバースに興味があるメンバーが集まってはいたのですが、プライベートで使い込んでいる人はいなかったので、「体験会を通じて、初めてメタバースがどのようなものか理解できた」という声が多く挙がっていました。

久保田:
メタバースという言葉がバズワード化し、定義が定まっていない中で、長谷工様は3Dデータを活用し、デジタルとリアルを繋ぐものとしてメタバースを活用しようとされています。その観点で言うと、体験会で「メタバースはこういうもので、こういう使い方ができるのではないか」という方向性を示すことができたのは大きかったと思います。
また、このプロジェクトは数年後を見据えた将来的な活用だけでなく、現在のビジネスでの活用も範疇としています。そうやって、将来と現在を行ったり来たりしながらメタバースの可能性を示せたことも、このプロジェクトの大きな意義だったと感じています。
――支援チームの皆さんにも伺いたいのですが、このメタバースという分野は理解が難しく、社内外への説明や交渉も困難だったと思います。システム開発やサービスデザインの観点から、特に難しかった点や、どのように乗り越えてきたのかをお聞かせください。
永井:
先進的な分野であるメタバースは、突き詰めると「システムの総合格闘技」のようなものになりがちです。今回のシステムでも、「3Dモデルで部屋の再現をする」「再現された空間で家具をコーディネートできるようにする」「アバターで動き回れるようにする」「コラボレーターである良品計画様のサイトと連携する」など、考慮すべき点が多くありました。
一方でメタバースは、インタラクティブな「ゲーム」のようなコンテンツと捉えられることもあります。もちろんそのような側面もありますが、それに加えて、業務システムや基幹システムといったセキュリティ面とビジネス要件を考慮する必要があった点も、今回のプロジェクトのポイントだったと思います。
現在は実際にユーザーの声を聞きながら改善を進めていますが、その中にはメタバースに慣れていないユーザーも少なくありません。お話を聞く限りでも、あくまでも「コーディネート」という目的を達成するための手段として、メタバースを利用する人が多い。そのような印象を受けました。そのため、UI/UXの作り込みがより重要になっており、今後も継続的な改善が必要だと感じています。
――今回、開発はアジャイル型で進められたとのことですが、長谷工様が通常業務システムを構築するプロセスとは異なっていたのではないかと思います。その点はいかがでしたか?
鈴木:
ICT活用推進部はアジャイル開発に慣れていますし、そもそも価値創生部門内でのトライアル的な取り組みであるため、特に抵抗感はなかったですね。
谷沖:
IT推進部でも、顧客向けの新規サービスに関しては、作りながら考えるアジャイル型での開発が多くなってきています。ただ、業務システムの場合は事前にしっかりと要件を定義する必要があるため、IT推進部全体としては、ウォーターフォール型の開発の割合が多くなっています。
――新しいことに挑戦できる土壌があったからこそ、スムーズに実証まで進められたということですね。椋野さんにも伺いたいのですが、サービスデザインの観点ではいかがでしょうか。難しかったポイントと、それをどう乗り越えたのか。
椋野:
構想段階では議論が中心で、アイデア出しやまとめ作業がメインだったので、そこまで苦労はありませんでした。問題は、形にする段階ですね。特に今回は先進的な取り組みであり、類似するサービスがないため、コンセプトをユーザーに理解してもらわなければなりません。メタバースではない既存のツールを使ってサービスの内容を伝えつつ、それに対するフィードバックをもらいながら進める必要があったため、形にするのが難しかったところです。
実際に使ったユーザーからは「ありそうでなかったサービスだ」「あったらすごく便利だね」という声を頂戴しているのですが、そのような価値をサービスに落とし込んでいく過程でも苦労しました。まだまだ改善の余地は残されているものの、コアとなる価値は伝わったのではないかと感じています。
――ユーザー価値設計においては、長谷工の社員の皆様にユーザーテストにご協力いただいたことが、早期実現に繋がった要因として大きかったですね。
椋野:
コストを抑えつつ、迅速に実施できた点は良かったと思います。
――実際に家をご購入された方も多く、迅速にインタビューをできたことは、サービス価値を高める上で非常に有効だったと思います。鈴木さんはいかがでしょうか?

鈴木:
入り口の段階で、まず「メタバースとは何か」を説明することが大きなハードルでした。これは今でも大きなハードルですね。
私自身は以前からXRやVRに取り組んでいたため、自分なりのメタバース観を持っていましたが、多くの人はそうではありません。実際にプロジェクトを進める中で「これってメタバースなの?」という質問は今もありますし、「“メタバース”と言っていいものなのか」と疑問に感じることもあります。とはいえ、最終的には「メタバース」という言葉にこだわらなくても良いとも考えています。
――メタバースという「手段」が最初に規定されている点が、このプロジェクトの難しさでもありますよね。ビジネス上は「価値」を生み出すことこそが重要であり、その実現手段は必ずしもメタバースである必要はありません。メタバースという手段を使うことで、いかに価値を生み出すのか。それが重要だと感じています。
鈴木:
社内での報告には必ずメタバースという言葉を使っているので、読んだ人はそれをメタバースとして捉えてくれています。ですが実際のところは、「これは本当にメタバースなのか?」と疑問に感じている部分もあるはずです。
谷沖:
「VRじゃダメなの?」と。
鈴木:
「まあ……VRですけどね!」と思う部分もありますね(笑)。
――その議論はありますよね。同時に推進している別の取り組みの話ではありますが、メタバース内覧では「VRの内覧」と「メタバースの内覧」を明確に区別し、メタバースならではの価値を生み出せるのかを検証しています。そういった意味では、本件においても「メタバース」だからこそ提供できる価値を追求することが重要だと考えています。
鈴木:
長谷工はマンション事業に特化し、マンション周辺の関連事業体が隙間なく配置されています。そのため「ターゲットをマンションにすると、必ずどこかの事業と競合してしまう」という問題があります。その際に、既存の事業に乗っかるか、その事業を超えるかという選択を迫られるため、事業化するまでには多くのハードルがあると感じています。
「より良いものを一緒に作り上げていく」ことの重要性
ポイント
・類似した成功例が少ない中で3社協業のプロジェクトが良いモデルケースになった理由
・今後サービスを拡大していく中で目指していくことは?
――今回、ドットアンドとMoguraが伴走させていただいたことで、どのような価値が生まれたと感じていますか? また、どのような成果に繋がりましたか? 鈴木さんと谷沖さんの所感をお聞かせください。
鈴木:
そもそも私たちだけでは走れないプロジェクトだったと思います。正直、ドットアンドさんとMoguraさんが一緒でなければ、どのように進めていけば良いのかすらわからないところがありました。今回のこのメタバースという分野に関しては、このチームで取り組むことの重要性が非常に大きかったと感じています。
谷沖:
そもそも長谷工は新規事業を立ち上げることに慣れておらず、メタバースの知識もなかったため、新規事業を進めるためのサポートに加えて、メタバースを構築するための知見が不可欠でした。私たちが抱く漠然とした要求を形にして提案していただいたり、プロジェクトをスピーディーに実現していただいたりと、大変お世話になりました。
――ありがとうございます。今回のプロジェクトは「コンサルタントとクライアント」という関係性ではなく、同じ目標に向かって協業をするような形で取り組めた実感があり、弊社としても良いモデルケースになったと感じています。その点について、他の外部業者様との協業経験と比較した際に、今回特に進めやすかった部分はありますか?
鈴木:
手前味噌ですが、弊社のチーム自体も良かったと思っています。私たちが提示したことに対して、コンサルタントの目線から頂戴したアドバイスをそのまま実践するのではなく、じっくりと練り込む姿勢を持っている。そんなメンバーが集まっていた点は大きかったですね。
正直に申しますと、ここまで長く続くかは懐疑的だった部分もありまして(笑)。最初は10人ほど集まりましたが、半分も残れば上々だと考えていました。メンバーに恵まれたことは大きかったですし、結局のところ、チームで重要なのは「人」だと感じています。
谷沖:
長谷工は会社としても保守的――という印象も若干あるのですが、外部から率直な意見を交換してくださったことで、我々としても一歩踏み出すことができたと感じています。
久保田:
多くのメタバースのプロジェクトを見てきた経験から言えることとして、「多くの事例が単発で終わってしまっている」という現状があります。手段が目的化してしまい、限られた予算や期間でメタバースに取り組むようなケースも少なくありません。また、同業他社の取り組みを真似るパターンも目立っており、ご相談をいただいた時点でやることや予算が決まっていて、本来の目的を達成するためのご提案ができない場合も多くあります。
その点、長谷工様の場合は「メタバースとは何か」をまずじっくりと議論し、実際に物件を購入されたお客様に対してアプローチを行うなど、踏み込んだ取り組みを短期間でされています。また、内製化すれば小さくまとまってしまいますが、今回も家具メーカー様を巻き込んでいるように、外部のパートナーと協力することでより大きな成果を目指されている点も、他にはなかなかない取り組みだと感じています。
実際の取り組みについても、「3Dのマップに3Dアセットを配置してインテリアコーディネートをする」というサービスが珍しくない中で、長谷工様は間取りのデータを活用したり、アバターを導入したりと、かなり踏み込んだ取り組みをされています。一般の事業者にとっては未知数のメタバースという分野に挑戦し、まだ世に出ていない新しい価値を創造しようとされていて、今もその取り組みが続いていると感じています。
――社内で新規事業を始める場合、その会社が持つアセットなどを活用してレバレッジをかけるのが基本だと思います。そんな中、実際に販売しているマンションでお客様に向けたサービスを短期間で提供できるのは、既存事業をしっかりと持っている長谷工様のような企業だからこそ可能な新規事業の試し方だと思っています。ゼロベースで立ち上げるスタートアップが真似しがたい強みであり、新規事業のあるべき姿だと感じました。
鈴木:
不動産というアセットを持ち、エンドユーザーとの距離も近く、各グループから集まった、現場を知っているメンバーが多いこと。それが弊社の強みだと思います。
今回のメタバースプロジェクトには3つの取り組みがありますが、そのほとんどは、現場を知っているメンバーが自分たちのやりたいことを提案したものです。そうやって、いろいろなパーツが組み合わさった結果でもあるのかなと思います。
――新しいものは、得てして「知っているもの×知らないもの」の掛け合わせによって生まれるもの。そう考えると、「メタバース」という未知のものを現場に投入し何ができるかを考えた今回のプロジェクトも、非常に興味深いアプローチであると思います。メタバースプロジェクト、およびメタバース家具コーディネートサービスの今後の展望について、お聞かせいただけますでしょうか。
鈴木:
最初に企画から始まり、実証実験の段階を経て、現在は3つのテーマでスモール実証を進めています。まずは実証実験の結果をしっかりと分析し、事業に繋げていくことが――経営陣へのアピールも含めて――非常に重要だと感じています。
ただ、その「成果」は必ずしも事業である必要はなく、もし「まだ早い」という結論が出たとしても、それもひとつの成果です。どのような結果であれ、何らかの答えを出すことにこだわって取り組んでいくことが肝要だと考えています。

谷沖:
現在のサービスの展望としては、様々なメーカー様にご協力いただき、いろいろなことを試せる空間を作った上で、家具のコーディネートだけではなく、さらに多種多様なサービスへと展開していければと考えています。
先日インタビューさせていただいた方からも、「この空間でこんなことができたら良いな」というご意見をたくさん頂戴したので、お客様からのご要望をメタバース空間内で展開していきたいと考えています。
――最後に、私と久保田さんから今後の展望についてコメントさせていただきます。現実世界で「マンション」というハードでナンバーワンである長谷工様が、メタバースで何かできないかを考えることは、非常にビジネス的な価値があると感じています。

家具コーディネートサービスは入り口のひとつではありますが、それを作ることだけが目的ではありません。たとえば「居住プラットフォーム」として考えた場合、バーチャル空間上に再現した部屋を使ってリフォームの提案をしたり、リアルとバーチャルが融合した新しいサービスを展開したりと、様々な可能性が考えられます。
すぐに収益に繋がるかどうかは議論が必要ですが、中長期的な視点で先進的なテーマに取り組むことは、ナンバーワンプレイヤーだからこそできるチャレンジです。その中で新しいことに挑戦し、業界をリードするような事業や知見を得ていくことは非常に重要です。我々もパートナーとしてそのようなチャレンジに貢献できればと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
久保田:
企画段階から実際に形にしていく過程では様々な意見が出ますが、ひとつのシステムに落とし込む際には、アイデアを絞り込む作業も欠かせません。その過程で一旦は見送る判断をすることもありますが、今は実装したものに対してフィードバックが返ってきていて、そこでまた新しいアイデアが生まれています。
ビジネス側の意見を形にしていくためには、技術的な裏付けが欠かせません。ビジネス的に価値のある、より良いものを作るには、両者のバランスを取りながら進めていくことが重要です。また、「こういう機能があったら良いのに」と言っていただけるのは、期待されていることの裏返しでもあると思うので、また使いたいと思っていただけるような、期待に応えられるようなものを作れればと考えています。そのような過程でご支援させていただけるのは弊社としてもありがたいことですし、忘れてはいけない部分だと考えています。
弊社としては、「言われたものをその通りに作る」という感覚はあまりなく、「より良いものを一緒に作り上げていく」という意識で取り組むことが重要です。メタバースはまだ成功事例が少ないため、それを「私たちが作っていく」という意識で取り組んでいきたいと考えています。技術面もどんどん進化しているので、そういった情報も定期的に提供させていただくことで、一緒にアイデアを創出していければと思います。

鈴木:
メタバースに良い事例が少ないのはなぜでしょう?
久保田:
「向き合いきれない」という理由が大きいと思います。あとは、すぐに結果が出ないため、諦めてしまって単発で終わってしまうパターンが多いですね。
実際、世の中では次々に新しい技術が登場しているため、メタバースよりも成果が出やすい分野に投資が集まる傾向があります。メタバースにも潜在的な可能性はありますが、「本当に活用できるのか」という疑問もあり、検討段階で終わってしまうケースが多いのだと思います。また、成功のためには様々な業界や周囲を取り巻く状況に合わせていく必要がありますが、事例自体が少ないため、成功パターンが見えにくいという現状もあります。
ある業界で成功した事例が、他の業界ではまったく通用しないため、誰もが真似できるような成功パターンが出てこないんですよね。
――逆に言えば、技術的なブレイクスルーがいつ起こるか分からないからこそ、ユーザー体験上で何が重要なのかを社内で蓄積しておくことが重要なポイントだと思います。
久保田:
先ほどの「これが“メタバース”なのかわからなくなる」というお話は、それが功を奏している部分もあると思います。たとえば、今作っている空間が「アバターでコミュニケーションを取る」ことを前提にしていた場合、それ以外の用途では使えませんし、価値検証も難しくなっていたはずです。
ですが、今回は「間取りをブラウザ上で見られる」「インテリアをカスタマイズできる」といった様々な機能を提供しつつ、その1つとして「コミュニケーション空間としても使えます」という機能が実装されています。コミュニケーション機能に価値が生まれるまでは時間がかかるかもしれませんが、空間自体に様々な活用方法があり、そこにユニークさを感じてもらえれば、今後より多くの人に利用してもらえる可能性があります。
鈴木:
今は「メタバース」という言葉を掲げて取り組んでいますが、最終的な目標はメタバースでなくても良いと考えています。我々の考えている出口は「成果」なので、「その先にメタバースがあるかもしれない」と意識しつつも、ステップバイステップで成果を出すことを目標に取り組んでいきたいと考えています。